太陽は銀河系の中では主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。
トゥルシーTulasi (Ocimum sanctum Linn.) 和名カミメボウキ トゥルシーの木とクリュシナ神の結婚
トゥルシーは普通緑だが、いくつかの種類があり、これは薬効が一番強いとされるクリュシナ・トゥルシー(黒いのでクリュシナの名がつけられている。写真真下)
トゥルシーの木とクリュシナ神を結婚させる…
象にのって楽隊を引き連れ、花嫁の元へ向かうターバンを巻いた新郎さん。そんな光景を町で見かけるようになったら、インドの結婚式シーズンのはじまりです。12月から1月くらいが結婚式のピーク。
インドの結婚式はとにかく派手!です。何日も続くパーティに、親戚一同が何枚もの着替えのサリーをもって集まります。(花嫁だけでなく、列席者も何度もお色直しをするのです!)ごちそうあり、音楽あり、ダンスあり!吉日ともなると、町のあちこちで大音響のパーティが夜通し行われて...睡眠不足~~~(@@)になることも、シバシバ。
でも、そんな人間様の結婚式シーズンがくる前に、大事な儀式がひとつあります。
それは各家にある、トゥルシーの木とクリュシナ神を結婚させることなんです。
木と神様を結婚させるって、ナニ??? って、思うでしょう?
町中の花屋さんでは、プージャ(儀式)に使うためにトウルシーが山積 みで売られている。純粋性が高く、浄化に役立つ聖なる植物とされて、儀式には欠かせない。
トゥ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 トゥルシ |
(学名)Ocimum Sanctum (日本名)カミメボウキ (英名)Holy Basil 旦那のいとこの子が、「ハーブの女王を知ってるか?」っと聞いてきました。 彼曰く、この女王のハーブを、家に飢えると、いい事が起こるというのです。 ということで、彼の家に行ってきました。 何のハーブかな?と思っていたら、トゥルシーでした。 彼の家の前には、たくさんのトゥルシが生えていました。 毎朝、ティに入れているそうです。 インドでは本当に家庭で大事にされているトゥルシー。 このハーブがあると、家族の健康が、このトゥルシだけで、守られているそうです。 はじめは、数本しかなかったトゥルシ。 種が落ちてすぐ増えたそうです。 |
| 私もその苗をもらって育てています。 いとこが言うには、「生理の女の人が、トゥルシーの木に触ったら、木がダメになる」んだそうです。 迷信だとは思うんですが、それほど、聖なる木なんですね。 ハーブティにして、飲むのも楽しみですけど、私の家の1番の目的は、蚊よけです!! トゥルシーは害虫よけの効能もあると聞いてから、絶対飢えようと思っていたハーブでした。 電気エネルギー持っていて、植物の中でオゾンを1番出す植物、絶対植えてみたくなります。 まだ、家のトゥルシーは、小さいですが、大きくなったころには、蚊が、いなくなることでしょう。オゾン層も小さな我が家から、少しでも増やして、地球もどんどん喜んでいくといいです!! トゥルシーはしそ科のオキウム属の多年草で、インド、アジアの熱帯地域で栽培されています。料理、薬、香料などの用途があります。 トゥルシの意味は、「比例なきもの」です。 新鮮な葉は、精神を落ち着かせ、ストレスと穏和する働きがあり、乾燥した葉も、免疫力を高め、気管支炎に効果があり、この薬効の多さに驚いて、西洋で、ホーリーバジルと呼ばれるようになったそうです。 ヒンドゥー教の家庭では、よくお庭にこのトゥルシーが栽培されています。 |
| 精なる木として崇められており、家庭の健康のために、植えられています。 家にトゥルシがあれば、心配事や、病気や、不幸はその家に入ることが出来ないといわれています。 またこのトゥルシの生えている周りは、空気を浄化する作用があるとされます。 トゥルシは、世界中の草の類で1番オゾンを発生するそうです。るので、この薬効の多さに また虫除けにもなり、蚊などが寄らないと言われます。 風邪の予防、体の耐久力の向上、殺菌、解毒、消化不良、感染症、鼻炎、咳などに効果があ り、喘息を穏和する特効薬としても使われてきました。 科学者により、強壮作用、免疫復活作用、ストレスに適応するからだの能力の上昇などが、実証されています。 トゥルシは、体に蓄積した毒素を、体外に排泄する働きがあって、ジュースを飲むと、体にたまった、水銀の有害物質を、中和するのだそうです。 アーユルヴェーダの賢人達は、インド国内において、トゥルシバンという活動を始めました。それは国内にトゥルシをたくさん栽培することで、健全な国づくりをしようとしたのです。 そして、21世紀に入り、聖者パパジ師が、インド古来の最重要神聖役のトゥルシーを世界に出すときがきた。特にやんだ国に広めよう。と言い出して、信者の中から、ミットラ氏を指名し、トゥルシーが、世界中に輸出されるようになったのです。 今ではいろんな国で、地球を浄化するため、健康のため、地球を救うために、植えだしたのです。 風邪っぽいときは、葉を生で食べ、食後に、お茶を飲みます。 また、葉を枕元におきて寝ると、蚊が寄ってこないんだそうです。 今の時代に、確実の重要な、アーユルヴェーダのハーブだと言えます。 |
|
-トゥルシー(粉、タブレット、カプセル入り)はサフランロードの店からお買い求めいただけます -
|
|
|
|
| * トゥルシは・・・電気エネルギーを持っていることなのです *トゥルシーは・・・ どんな副作用もおこさないことで有名です。 *ホーリー・バジルは・・・『医者いらずの薬草』、あるいは、『生活の霊薬』と呼ばれる |
|
| マサラ | ヨーグルト | ギー | バターミルク | ラッシー | チャイ | ジャグリ蜜 | パニール | グルテン | セイタン |
| ごま塩 | 豆腐 | 豆乳 | 味噌 | 練りごま | 納豆 | 漬け物 | パン | アーモンド | コーフー |
| このサイトはヤフー登録サイトです |
| ◆アーユルヴェーダ ◆おもしろインド ◆マクロビオティック ◆セイタン ◆更新情報 ◆リンク集 |
| アーユルヴェーダ のベストセラー! インドパワーの源泉 ハーブやミネラル で元気に テルになっていた。20ルピー払うことで宿泊客以外でも中を見ることができる。だが、見所に乏しい城であった。ドゥンドロードはどうもポロで有名らしい。城の正門前はバーザールになっており、いくつか立派なハヴェーリーも建っていたが、先を急いでいたので中は見なかった。
ドゥンドロードからさらに北上すると、ムクンドガルという町に出た。ここで多少迷ったが、マンダーワー行きの道を探し出してマンダーワーへ向かった。特に問題なくマンダーワーに到着し、街中を通らずにファテープルへ行く道を取った。マンダーワーからは普通シヴァリンガであるが、ここだけは人間の姿でシヴァが祀られているとか。しかもイタリアから輸入した大理石で作られている。また、寺院の外壁と内壁の一部にはやはりフレスコ画が描かれていた。ラグナート寺院から5分ほど歩いた場所にはサハージ・ラーム・ポーダールのチャトリーという遺跡があったが、こちらは特筆すべき事柄はなかった。
さて、夕食の時間になった。ホテルの主人のマヘーシュワル氏が焚き火に当たっていたので、僕もそれに参加してボチボチ話を始めた。マヘーシュワル氏が「ビールは飲むか?」と聞いて来たので、「今だ!」と思ってファテープルのメヘラージ氏の名前を出し、メヘンサル特産の酒を飲みたいと言ってみた。そうしたら案外簡単に出してくれもたらされた文明の利器が描かれていたが、ここのハヴェーリーの絵は最も面白い。車に加えて、飛行機や電話なども描かれているのだ。ベルが電話を発明したのが1876年、ライト兄弟が初めて飛行に成功したのは1903年、この絵が描かれたのは1920年頃らしい。当時のインドの田舎町としては最新の技術だったことだろう。そしておそらく実物を見たことがない絵描きがこれらの絵を描いたのだろう。列車の絵もそうだったが、これらの絵は、町の人々に世界でどんなことが起こっているのかを教えるためのものだったらしい。 点に駐車場があり、そこから10分ほど歩くと到着する。ナルマダー河にあるこの滝は、「煙の滝」という名前の通り、ものすごい水しぶきを上げる豪快な滝であった。ここは観光地であると同時に周辺住民の生活の場でもあるようで、地元の人々が河で洗濯したり水浴びしたりしていた。 点に駐車場があり、そこから10分ほど歩くと到着する。ナルマダー河にあアーナンド、クマール を使った、電話回線のない家庭用電話があるので、こういうことができる。しかもヒンディー語で「ヴィクラーング(विकलांग)」と書かれている。「身体障害者」という意味だ。つまり、これは身体障害者が運営する移動式電話屋なのである。この三輪車みたいな乗り物は、足の不自由な人が乗る車椅子で、車両行き交う道路を勇敢に走っている姿を時々見かける。足ではなく、手でこぐようになっている。だが、それを移動式電話屋にしてしまうとは、なかなかグッドアイデアである。しかも、病院の前で出店していた。何から何までグッドアイデア尽くしである。
バスや自動車が行き交う道路を悠々と進んで行くラクダ兵団は、ものすごくかっこよかった。ラクダは砂漠だけでなく、舗装道にもよく映える生き物だ。思わず追いかけて行って、何とか前から写真を撮った。
だが、あまり知られていないが、モスクなどに併設されている塔を除けば、デリーには少なくともあと2本、古い塔が建っている。今日はその2本の塔を求めて旅立った。 上段左から、シャノンとゴーヴィンダー、
備考:PVRプリヤーで鑑賞。 このブログの更新通知を受け取る場合はここをクリック
ソハイル・カーン(左)とスネーハー・ウッラール(右)
るこの滝は、「煙の滝」という名前の通り、ものすごい水しぶきを上げる豪快な滝であった。ここは観光地であると同時に周辺住民の生活の場でもあるようで、地元の人々が河で洗濯したり水浴びしたりしていた。
ドゥアーンダール滝から少し戻ったところの丘の上には、64ヨーギニー寺院という円形の寺院がある。円形の壁には64体のヨーギニーの像が」「ここでレーカー(女優の名前)が踊りました」「あそこの洞穴にはワニが住んでいますが、今は夏休みでどこかへ行っています」などと、ヒンディー語で面白おかしく解説をしてくれる。遊覧客に披露するためか、それともただ単に暑いからか知らないが、子供たちが岩の上から飛び込み合戦をしていたのが一番印象に残った。時間は正味30分ほど。以前はもっと奥まで行っていたようだが、上流にナルマダー・ダムが出来たおかげで水位が下がり、今は途中までしか行けなくなってしまっているらしい。はっきり言って面白さは期待を下回ったが、インドの数ある観光地の中でもユニークなアトラクションだと感じた。このベーラーガート遊覧は10月から6月まで営業している。
ベーラーガートはジャバルプルから約22kmの地点にあるが、遊覧を終、狭い敷地内に、ヒンドゥー教の神様たちの巨大な人形がいくつも並べられている。そしてそれらの造形のレベルがインドにしてはなかなか高い。バスの中からは、2つの寺院の屋上にある巨大なハヌマーンとシヴァの像のみが目に入ったのだが、敷地内には他にもヴィシュヌ、クリシュナ、ブラフマーなど、多くの神様の人形があった。
しかし、それらのハイレベルな神様人形よりも面白かったのは、このバンジャーリー寺院のご本尊である。つい、これらの人形に圧倒されてしまうが、バ理に来てしまった。花の谷と同じく、やはり自然モノの観光地は季節を外して行くと楽しさと感動が半減以下になってしまうことを痛感させられた。
もし滝が少しでも豪快に流れていたら、午後4時発のバスまでここでゆっくりしていこうかと考えていたが、滝がこのような状態だったので、早めに切り上げて帰ることにした。つまり、11時発のバスでジャグダルプルへ帰ることにした。
とりあえず今日は見るだけにして、何も買わなかった。その後はサンジャイ・マーケットを散策して、いかにも部族っぽい人の写真を激写することに精を出した。
次に、コータムサル洞窟へ行った。コータムサル洞窟への入り口をくぐをシヴァリンガや神像に見立てた祠があった。こういうオチの付け方がいかにもインドらしいところで僕は気に入った。観光客用に整備されていないことが功を奏して洞窟全体がかなり天然のまま残っているし(人工物は階段のみ)、電灯などが設置されておらず、ライト係が持っている懐中電灯と蛍光灯のみがを頼りとして歩いて行く状態なので、まるで洞窟を探検しているような気分になれる。
もったいぶってしまったが、実はこのマイナー鳥、日本語で言う九官鳥のことである。どうも九官鳥の原産地はインドのこのバスタル地方のようだ。日本で九官鳥と言ったら誰でも少なくとも「人間の言葉を真似するあの黒い鳥か」とイメージできると思うのだが、なぜか原産地のはずのインドでは、九官鳥はあまりメジャーではない。よって、鳥が人間の言葉をしゃべることに大半のインド人は大いに驚くらしい。係員の話では、この森林大学に飼育されていた九官鳥高いが、心配していたほど肌寒くもない。それよりもじめっとした湿気がまず感覚に触れた。町の建物も湿った感じだ。メーガーラヤ州の州都シロンに似た雰囲気の町だと感じた。
マディケーリには、政府系バススタンドと私営バススタンドの2つがあり、両者はすぐ近くにある。政府系バススタンドの方が町の奥まった場所の低地にあり、私営バススタンドは繁華街の入り口に位置している。マディケーリのホテル、レストラン、お土産屋などは、この私営バススタンドの近くに集中しており、旅行者にはとても便利である。僕はマディケーリのホテルの中でも老舗っぽいホテル・カーヴェーリーに宿泊した。ダブルルーム、バストイレ、TV、タオル、石鹸など付いて450ルピー。バスルームにはギザはなく、バケツにお湯を持ってきてもらう方式である。町の外観に負けず劣らずじめっとした部屋であった。ホテルのマネージャーは旅行者の扱いに慣れており、専属オートリクシャーを使ったツアーやトレッキングもアレンジしてくれるようだ。だが、ホテルは悪い意味で開放的な作りになっており、あまりいい雰囲気ではなかった。
アッビ滝を見た後は来た道を引き返し、マディケーリ郊外の小高い山の上にあるガッディゲ(王の墓)へ行った。ここには一見イスラーム様式に見える墓が3つ並んでいる。
だが、面白いことにこれらはイスラーム教徒の墓ではない。18世紀末~19世紀初めにコダグ地方を支配したヒンドゥーの王や僧侶の墓である。通常、ヒンドゥー教徒は墓を作らないと言われているが、コダヴァが信仰しているのは少し特殊なヒンドゥー教のようで、このような形で墓が残っている。また、バンガロールではヒンドゥー教徒のための墓地も目にした。この辺りのヒンドゥー教は北インドとはかなり習慣が異なるかもしれない。ガッディゲの墓にはドームを中心として4本のミーナール(尖塔)が立っているが、ミーナールにはナンディーうな形で墓が残っている。また、バンガロールではヒンドゥー教徒のための墓地も目にした。この辺りのヒンドゥー教は北インドとはかなり習慣が異なるかもしれない。ガッディゲの墓にはドームを中心として4本のミーナール(尖塔)が立っているが、ミーナールにはナンディー(雄牛)が彫刻されている。コダグの王はシヴァ神の信徒だったようで、内部には墓らしき土台(?)と並んでシヴァリンガが祀られていた。その他、ナーガ(蛇)に乗ったシヴァ神の彫刻や、シヴァリンガをなめる牛の彫刻などがあった。これら3つの墓の中で、中央の最も大きな墓は、ヴィーララージェンドラ王(在位1789-1809年)とその后マハーデーヴィー・アンマーのもので、その両側の墓は、ヴィーララージェーンドラ王の弟、リンガラージェーンドラ2世と、ヴィーララージェンドラ王のグル(導師)だった僧侶ルドラッパのものである。どれも19世紀前半の建造だ。
その次はオームカーレーシュワル寺院へ行った。この寺院の建立を巡ってはひとつの言い伝えがある。リンガラージェーンドラ2世はあるとき、自分の間違いを諌めた大臣の僧侶を斬首したことがあった。そのときから王は僧侶の亡霊に昼夜問わず悩まされるようになった。王はある賢人の助言に従い、カーシー(ヴァーラーナスィー)からシヴァリンガを取り寄せ、それを祀った寺院を1820年に建立した。すると、王は僧侶の亡霊から解放されたという。これがオームカーレーシュワル寺院建立秘話である。
オームカーレーシュワル寺院の境内には、まず正方形の池があり、その中心にはクシャル・マンダパと呼ばれる祠堂が浮かんでいる。祠堂は1本の通路で外縁部と結ばれており、その様子はまるでアムリトサルの黄金寺院のようである。祠堂の中にはシヴァとパールワティーと思われる像が納められていの黄金寺院のようである。祠堂の中にはシヴァとパールワティーと思われる像が納められていた。寺院の本殿へは階段を上っていく。本殿は四方を壁で囲われており、まるでイスラーム建築のような門が池に面して建てられている。本殿もやはり4本のミーナールとドームを持ったイスラーム様式の建築だが、それ以外はヒンドゥー教寺院そのものである。本殿入り口の真ん前には、バリピータと呼ばれる祭壇もあった。
本殿の外壁には、いくつか面白い彫刻を見つけた。全て銀色に着色されて言に従い、カーシー(ヴァーラーナスィー)からシヴァリンガを取り寄せ、それを祀った寺院を1820年に建立した。すると、王は僧侶の亡霊から解放されたという。これがオームカーレーシュワル寺院建立秘話である。
オームカーレーシュワル寺院の境内には、まず正方形の池があり、その中心にはクシャル・マンダパと呼ばれる祠堂が浮かんでいる。祠堂は1本の通路で外縁部と結ばれており、その様子はまるでアムリトサルの黄金寺院のようである。祠堂の中にはシヴァとパールワティーと思われる像が納められていた。寺院の本殿へは階段を上っていく。本殿は四方を壁で囲われており、まるでイスラーム建築のような門が池に面して建てられている。本殿もやはり4本のミーナールとドームを持ったイスラーム様式の建築だが、それ以外はヒンドゥー教寺院そのものである。本殿入り口の真ん前には、バリピータと呼ばれる祭壇もあった。
本殿の外壁には、いくつか面白い彫刻を見つけた。全て銀色に着色されていた。
オームカーレーシュワル寺院の次に行ったのはラージャーズ・シート(王の座)と呼ばれるヴューポイント。小高い丘の上に花々で彩られた公園があり、コダグ地方の美しい緑のカーペットを展望することができる。公園の中に小さな東屋が建っているが、かつて王が后と共に夕方ここで夕日を眺めながら自然の美を愛でたと言われている。ここがラージャーズ・シートと呼ばれるのもそのためだ。この公園は花壇がきれいに整備されているが、毎年ここでフラワーショーが開催されるらしい。
最後に行ったのは要塞と宮殿。マディケーリがコダグの首都となったのは、ハーレーリ王朝第3代ムッドゥラージャ(在位1633-1687年)の時代の1681年であり、彼が最初にここに要塞と宮殿を建造した。そのため、マディケーリは当初ムッドゥラージャケーリ(ムッドゥラージャの町)と呼ばれていた。それが訛ってマディケーリとなり、英国人は「Mercara」と呼んだという訳だ。コダグがマイソール王国のティープー・スルターンの支配下に入ったとき、マディケーリはザファラーバードと呼ばれたこともあった。要塞は元々土造りだったが、ティープー・スルターンの時代に現存している六角形プランの形に再建された。六角形の城壁の頂点には円形のブルジ(小塔)が設けられている。また、現存している宮殿は1812~14年に再建されたもので、宮殿は現在では政府の庁舎となっている。宮殿は赤瓦の屋根の2階建ての建物で、ヨーロッパの建築の影響が見受けられる。宮殿の中央部にある中庭の中心部には、チョコンと亀の像が置かれている。これはトラヴァンコール・トートイズという西ガート山脈特有の種らしい。
また、要塞内には教会があり、現在では博物館となっている。小さな博物館で、展示物の数も少なかったが、ひとつ目に留まった展示物があった。それは、陸軍元帥KMカリアッパ(K.M. Cariappa)関係の展示物。カリアッパの像をマディケーリの他の場所でも見かけ、興味が沸いた。調べてみたら、カリアッパはインド軍事史の中でも最大級の英雄扱いの偉人であった。1899年1月28日、コダヴァ地方に生まれたカリアッパは、独立前は英国の信任け輝かしい業績を残したカリアッパが地元コダグ地方の人々から愛されるのも不思議ではない。また、KMカリアッパの息子、KCカリアッパも有名な空軍元帥のようだ。
要塞内で他に目立つものと言ったら、北東の隅に置かれている現物サイズの2匹の象の像である。解説によると、ヴィーララージェーンドラ王は所有していた2匹の象を何らかの理由で殺してしまい、それを悔いて作らせたものらしい。
ついでなので、ここでコダグの王朝史について簡単に触れておく。コダグ地方に比定される地名が文献に登場するのは2世紀頃らしく、それ以来、パーー、ジャム、オムレツに加え、プーリーとバージーまで出て来た。飲み物はもちろんコーヒー。コダグ地方はコーヒーを産出しているだけあって、コーヒーがうまい。
マネージャーの解説によると、キャピトル・ヴィレッジ・リゾートには2種類のコーヒーの木が植えられている。ひとつはアラビカ種、もうひとつはロブスタ種である。アラビカ種の方が葉は小さいのだが、実は大きい。味は、アラビカ種はマイルドな一方で、ロブスタ種は強い。アラビカ種が30年ほどで実を付けなくなってしまうのに対し、ロブスタ種は150年は収穫可能だという。どちらも日本でよく流通しているコーヒー豆みたいだ。あまりコーヒーには詳しくなかったのだが、コーヒー・プランテーションに植えてあるコーヒーの木を見ながら解説してもらうと、よく分かった。
コーヒー・プランテーションは見学することができたのだが、コダヴァ族の村を訪れることは適わなかった。チャッティースガル州と同じく、部族の村を訪れるツア機会を得る。それはなかなかうまく行かないのだが、最後には一攫千金に成功し、3人は金持ち生活を送るようになる。「Phir
Hera Pheri」は、3人が金持ちになった少し後から始まる。
ドゥアーンダール滝から少し戻ったところの丘の上には、64ヨーギニー寺院という円形の寺院がある。円形の壁には64体のヨーギニーの像が」「ここでレーカー(女優の名前)が踊りました」「あそこの洞穴にはワニが住んでいますが、今は夏休みでどこかへ行っています」などと、ヒンディー語で面白おかしく解説をしてくれる。遊覧客に披露するためか、それともただ単に暑いからか知らないが、子供たちが岩の上から飛び込み合戦をしていたのが一番印象に残った。時間は正味30分ほど。以前はもっと奥まで行っていたようだが、上流にナルマダー・ダムが出来たおかげで水位が下がり、今は途中までしか行けなくなってしまっているらしい。はっきり言って面白さは期待を下回ったが、インドの数ある観光地の中でもユニークなアトラクションだと感じた。このベーラーガート遊覧は10月から6月まで営業している。
ベーラーガートはジャバルプルから約22kmの地点にあるが、遊覧を終、狭い敷地内に、ヒンドゥー教の神様たちの巨大な人形がいくつも並べられている。そしてそれらの造形のレベルがインドにしてはなかなか高い。バスの中からは、2つの寺院の屋上にある巨大なハヌマーンとシヴァの像のみが目に入ったのだが、敷地内には他にもヴィシュヌ、クリシュナ、ブラフマーなど、多くの神様の人形があった。
しかし、それらのハイレベルな神様人形よりも面白かったのは、このバンジャーリー寺院のご本尊である。つい、これらの人形に圧倒されてしまうが、バ理に来てしまった。花の谷と同じく、やはり自然モノの観光地は季節を外して行くと楽しさと感動が半減以下になってしまうことを痛感させられた。
もし滝が少しでも豪快に流れていたら、午後4時発のバスまでここでゆっくりしていこうかと考えていたが、滝がこのような状態だったので、早めに切り上げて帰ることにした。つまり、11時発のバスでジャグダルプルへ帰ることにした。
とりあえず今日は見るだけにして、何も買わなかった。その後はサンジャイ・マーケットを散策して、いかにも部族っぽい人の写真を激写することに精を出した。
次に、コータムサル洞窟へ行った。コータムサル洞窟への入り口をくぐをシヴァリンガや神像に見立てた祠があった。こういうオチの付け方がいかにもインドらしいところで僕は気に入った。観光客用に整備されていないことが功を奏して洞窟全体がかなり天然のまま残っているし(人工物は階段のみ)、電灯などが設置されておらず、ライト係が持っている懐中電灯と蛍光灯のみがを頼りとして歩いて行く状態なので、まるで洞窟を探検しているような気分になれる。
もったいぶってしまったが、実はこのマイナー鳥、日本語で言う九官鳥のことである。どうも九官鳥の原産地はインドのこのバスタル地方のようだ。日本で九官鳥と言ったら誰でも少なくとも「人間の言葉を真似するあの黒い鳥か」とイメージできると思うのだが、なぜか原産地のはずのインドでは、九官鳥はあまりメジャーではない。よって、鳥が人間の言葉をしゃべることに大半のインド人は大いに驚くらしい。係員の話では、この森林大学に飼育されていた九官鳥高いが、心配していたほど肌寒くもない。それよりもじめっとした湿気がまず感覚に触れた。町の建物も湿った感じだ。メーガーラヤ州の州都シロンに似た雰囲気の町だと感じた。
マディケーリには、政府系バススタンドと私営バススタンドの2つがあり、両者はすぐ近くにある。政府系バススタンドの方が町の奥まった場所の低地にあり、私営バススタンドは繁華街の入り口に位置している。マディケーリのホテル、レストラン、お土産屋などは、この私営バススタンドの近くに集中しており、旅行者にはとても便利である。僕はマディケーリのホテルの中でも老舗っぽいホテル・カーヴェーリーに宿泊した。ダブルルーム、バストイレ、TV、タオル、石鹸など付いて450ルピー。バスルームにはギザはなく、バケツにお湯を持ってきてもらう方式である。町の外観に負けず劣らずじめっとした部屋であった。ホテルのマネージャーは旅行者の扱いに慣れており、専属オートリクシャーを使ったツアーやトレッキングもアレンジしてくれるようだ。だが、ホテルは悪い意味で開放的な作りになっており、あまりいい雰囲気ではなかった。
アッビ滝を見た後は来た道を引き返し、マディケーリ郊外の小高い山の上にあるガッディゲ(王の墓)へ行った。ここには一見イスラーム様式に見える墓が3つ並んでいる。
だが、面白いことにこれらはイスラーム教徒の墓ではない。18世紀末~19世紀初めにコダグ地方を支配したヒンドゥーの王や僧侶の墓である。通常、ヒンドゥー教徒は墓を作らないと言われているが、コダヴァが信仰しているのは少し特殊なヒンドゥー教のようで、このような形で墓が残っている。また、バンガロールではヒンドゥー教徒のための墓地も目にした。この辺りのヒンドゥー教は北インドとはかなり習慣が異なるかもしれない。ガッディゲの墓にはドームを中心として4本のミーナール(尖塔)が立っているが、ミーナールにはナンディーうな形で墓が残っている。また、バンガロールではヒンドゥー教徒のための墓地も目にした。この辺りのヒンドゥー教は北インドとはかなり習慣が異なるかもしれない。ガッディゲの墓にはドームを中心として4本のミーナール(尖塔)が立っているが、ミーナールにはナンディー(雄牛)が彫刻されている。コダグの王はシヴァ神の信徒だったようで、内部には墓らしき土台(?)と並んでシヴァリンガが祀られていた。その他、ナーガ(蛇)に乗ったシヴァ神の彫刻や、シヴァリンガをなめる牛の彫刻などがあった。これら3つの墓の中で、中央の最も大きな墓は、ヴィーララージェンドラ王(在位1789-1809年)とその后マハーデーヴィー・アンマーのもので、その両側の墓は、ヴィーララージェーンドラ王の弟、リンガラージェーンドラ2世と、ヴィーララージェンドラ王のグル(導師)だった僧侶ルドラッパのものである。どれも19世紀前半の建造だ。
その次はオームカーレーシュワル寺院へ行った。この寺院の建立を巡ってはひとつの言い伝えがある。リンガラージェーンドラ2世はあるとき、自分の間違いを諌めた大臣の僧侶を斬首したことがあった。そのときから王は僧侶の亡霊に昼夜問わず悩まされるようになった。王はある賢人の助言に従い、カーシー(ヴァーラーナスィー)からシヴァリンガを取り寄せ、それを祀った寺院を1820年に建立した。すると、王は僧侶の亡霊から解放されたという。これがオームカーレーシュワル寺院建立秘話である。
オームカーレーシュワル寺院の境内には、まず正方形の池があり、その中心にはクシャル・マンダパと呼ばれる祠堂が浮かんでいる。祠堂は1本の通路で外縁部と結ばれており、その様子はまるでアムリトサルの黄金寺院のようである。祠堂の中にはシヴァとパールワティーと思われる像が納められていの黄金寺院のようである。祠堂の中にはシヴァとパールワティーと思われる像が納められていた。寺院の本殿へは階段を上っていく。本殿は四方を壁で囲われており、まるでイスラーム建築のような門が池に面して建てられている。本殿もやはり4本のミーナールとドームを持ったイスラーム様式の建築だが、それ以外はヒンドゥー教寺院そのものである。本殿入り口の真ん前には、バリピータと呼ばれる祭壇もあった。
本殿の外壁には、いくつか面白い彫刻を見つけた。全て銀色に着色されて言に従い、カーシー(ヴァーラーナスィー)からシヴァリンガを取り寄せ、それを祀った寺院を1820年に建立した。すると、王は僧侶の亡霊から解放されたという。これがオームカーレーシュワル寺院建立秘話である。
オームカーレーシュワル寺院の境内には、まず正方形の池があり、その中心にはクシャル・マンダパと呼ばれる祠堂が浮かんでいる。祠堂は1本の通路で外縁部と結ばれており、その様子はまるでアムリトサルの黄金寺院のようである。祠堂の中にはシヴァとパールワティーと思われる像が納められていた。寺院の本殿へは階段を上っていく。本殿は四方を壁で囲われており、まるでイスラーム建築のような門が池に面して建てられている。本殿もやはり4本のミーナールとドームを持ったイスラーム様式の建築だが、それ以外はヒンドゥー教寺院そのものである。本殿入り口の真ん前には、バリピータと呼ばれる祭壇もあった。
本殿の外壁には、いくつか面白い彫刻を見つけた。全て銀色に着色されていた。
オームカーレーシュワル寺院の次に行ったのはラージャーズ・シート(王の座)と呼ばれるヴューポイント。小高い丘の上に花々で彩られた公園があり、コダグ地方の美しい緑のカーペットを展望することができる。公園の中に小さな東屋が建っているが、かつて王が后と共に夕方ここで夕日を眺めながら自然の美を愛でたと言われている。ここがラージャーズ・シートと呼ばれるのもそのためだ。この公園は花壇がきれいに整備されているが、毎年ここでフラワーショーが開催されるらしい。
最後に行ったのは要塞と宮殿。マディケーリがコダグの首都となったのは、ハーレーリ王朝第3代ムッドゥラージャ(在位1633-1687年)の時代の1681年であり、彼が最初にここに要塞と宮殿を建造した。そのため、マディケーリは当初ムッドゥラージャケーリ(ムッドゥラージャの町)と呼ばれていた。それが訛ってマディケーリとなり、英国人は「Mercara」と呼んだという訳だ。コダグがマイソール王国のティープー・スルターンの支配下に入ったとき、マディケーリはザファラーバードと呼ばれたこともあった。要塞は元々土造りだったが、ティープー・スルターンの時代に現存している六角形プランの形に再建された。六角形の城壁の頂点には円形のブルジ(小塔)が設けられている。また、現存している宮殿は1812~14年に再建されたもので、宮殿は現在では政府の庁舎となっている。宮殿は赤瓦の屋根の2階建ての建物で、ヨーロッパの建築の影響が見受けられる。宮殿の中央部にある中庭の中心部には、チョコンと亀の像が置かれている。これはトラヴァンコール・トートイズという西ガート山脈特有の種らしい。
また、要塞内には教会があり、現在では博物館となっている。小さな博物館で、展示物の数も少なかったが、ひとつ目に留まった展示物があった。それは、陸軍元帥KMカリアッパ(K.M. Cariappa)関係の展示物。カリアッパの像をマディケーリの他の場所でも見かけ、興味が沸いた。調べてみたら、カリアッパはインド軍事史の中でも最大級の英雄扱いの偉人であった。1899年1月28日、コダヴァ地方に生まれたカリアッパは、独立前は英国の信任け輝かしい業績を残したカリアッパが地元コダグ地方の人々から愛されるのも不思議ではない。また、KMカリアッパの息子、KCカリアッパも有名な空軍元帥のようだ。
要塞内で他に目立つものと言ったら、北東の隅に置かれている現物サイズの2匹の象の像である。解説によると、ヴィーララージェーンドラ王は所有していた2匹の象を何らかの理由で殺してしまい、それを悔いて作らせたものらしい。
ついでなので、ここでコダグの王朝史について簡単に触れておく。コダグ地方に比定される地名が文献に登場するのは2世紀頃らしく、それ以来、パーー、ジャム、オムレツに加え、プーリーとバージーまで出て来た。飲み物はもちろんコーヒー。コダグ地方はコーヒーを産出しているだけあって、コーヒーがうまい。
マネージャーの解説によると、キャピトル・ヴィレッジ・リゾートには2種類のコーヒーの木が植えられている。ひとつはアラビカ種、もうひとつはロブスタ種である。アラビカ種の方が葉は小さいのだが、実は大きい。味は、アラビカ種はマイルドな一方で、ロブスタ種は強い。アラビカ種が30年ほどで実を付けなくなってしまうのに対し、ロブスタ種は150年は収穫可能だという。どちらも日本でよく流通しているコーヒー豆みたいだ。あまりコーヒーには詳しくなかったのだが、コーヒー・プランテーションに植えてあるコーヒーの木を見ながら解説してもらうと、よく分かった。
コーヒー・プランテーションは見学することができたのだが、コダヴァ族の村を訪れることは適わなかった。チャッティースガル州と同じく、部族の村を訪れるツア機会を得る。それはなかなかうまく行かないのだが、最後には一攫千金に成功し、3人は金持ち生活を送るようになる。「Phir
Hera Pheri」は、3人が金持ちになった少し後から始まる。
英国人の来訪は、これまで神話や伝承などを題材にしていたシェーカーワーティー地方のフレスコ画に大きな影響を与えた。題材への影響は上に見てきた通りである。だが、その影響は題材だけでなく、絵の手法にも及んだ。1840年頃にインドに徐々に普及し始めた写真機は、今まで2次元だったシェーカーワーティー地味。監督はマニーシュ・シャルマー(新人)、音楽はサージド・ワージド。キャストは、イムラーン・ハーシュミー、セリナ・ジェートリー、リシター・バット、マヘーシュ・マーンジュレーカル、ティックー・タルサニヤーなど。
|
 ヒマラヤの神秘 シラジット |
 お釈迦さまになる!? 沙羅双樹クリーム |
 元気がでてくる アシュワガンダ |
 さすと痛い?痛快! インドの目薬 |
 記憶力増進! ブラフミー |
 ニコチン・フリー のスパイス煙草 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルシーは、1年性の草ですが、大きく茂るので、ちょっとした低木のようになる草です。インドでは、どこの家でもベランダに1本くらいはこの木を育てていて、神聖な木としてあがめますし、薬草として、家族の健康にも役立てています。
周囲の空気を浄化し、精神的な霊性も高めるトゥルシーは葉っぱ一枚で充分
朝、トゥルシーの葉を一枚たべると風邪をひかない、病気をしない、というので、ハチミツをつけたトゥルシーの葉を子供の口の中に押し込んでやるのはお父さんの役目。抗菌作用が強く、発汗、解毒作用をはじめとして、長いリストが出来るほど、多くの薬効があるトゥルシーは、生のままで食べる、絞り汁を飲むのが一番効果的。長く煎じると香りや薬効が薄れてしまうので、お茶にする時にも、コップの中にいれた葉っぱや、葉の粉にお湯を注ぐ程度にしていただきます。これ一本あれば、周囲の空気を浄化し、精神的な霊性も高めるということで、どこの家でも大事に鉢植えが育てられています。(注:ただしラットによる実験では生殖能力が落ちるという結果も。Indian J Physiol Pharmacol. 1992Apr;36(2):109-11.大量に食べ過ぎるとピッタをあげてしまうので、1枚で充分。神話では、トゥルシーの葉っぱ1枚で、クリュシナ神の重さと釣り合うほどだと書かれているので,とりすぎないこと)
牛糞で作った祭壇に祀られているトウルシーの木。根元をクムクムで赤 く塗り、毎日灯明や線香が捧げられ、礼拝の対象になっている。
神様と結婚させてから、人間の結婚シーズンをはじめる。そして、ガラスの腕輪…
特に、クリュシナ神が大好きな木なので、クリュシナ神の化身であるヴイシュヌ神の妻ラクシュミーに見立てて花嫁衣装をつけさせ、神様と結婚させてから、人間の結婚シーズンをはじめるのです。
木の根元には、既婚者の印である赤いクムクム(色粉)でお化粧し、綿で作った軽い首飾りをかけ、木に負担にならない程度の、軽くて小さなガラスのバングル(腕輪)をつけさせます。
腕輪屋さんに行くと、こんなに小さな腕輪は、いったい誰がするんだろう?というくらい小さな軽い腕輪が隅の方で売られていますが、それはこの木のための腕輪なのです。
その昔、大家族で一緒に住んでいたインドでは、ひとつ屋根の下に、軽く20~30人、多ければ100人近い人達が一緒に暮らしていました。そんな中で新婚の夫と二人だけで過ごすのは至難の業。そこで、花嫁は家事をしながら、他の人にはそれと気づかれないように、ガラスの腕輪をシャラシャラと鳴らして、二人だけにわかる秘密の合図を送り、こっそり裏の井戸べりで逢瀬を楽しんだりしたわけです。だから、花嫁に腕輪はつきもの。
トゥルシーの木が風にゆれて、ガラスのバングルがシャラシャラ音をたてています。愛するクリュシナをよんでいるのかな....
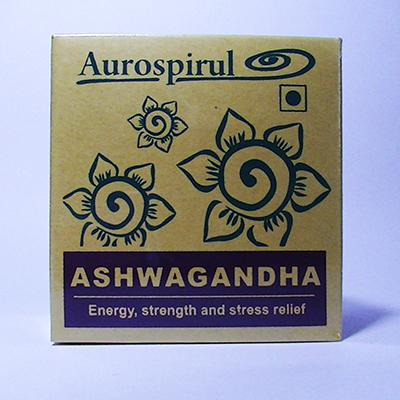













コメント
コメントを投稿